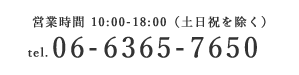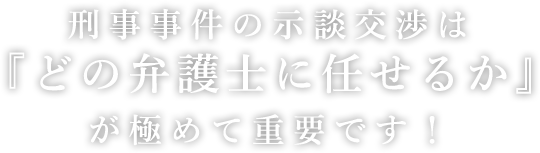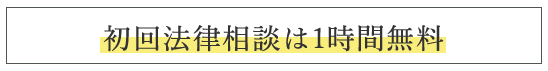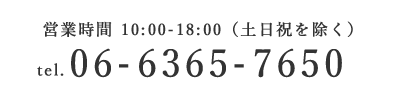起訴前勾留・被疑者勾留とはどういうものですか
-
逮捕に引き続き被疑者の身体を拘束する強制処分のことです。10~20日間拘束され、その後釈放されるか、起訴されるかが決まります。
詳細な回答
逮捕された被疑者が送検されると、次は検察官が「勾留」というより長期の身柄拘束を行う必要があるか否かを判断します。
逃亡や罪証隠滅のおそれありとして勾留を行う必要があると判断した場合、検察官は裁判官に対して勾留請求を行います。
勾留請求がなされると、被疑者は護送車に乗せられて裁判所に移動します。
そこで裁判官と面接し、事件に関するいくつかの質問(勾留質問)を受けます。
何人もの被疑者を一度にまとめて護送して順次勾留の手続を進めていくので、留置されている警察署に戻るまでかなりの時間がかかります。
裁判所から離れた警察署に留置されている場合、昼過ぎに出発しても他の全ての被疑者の勾留手続が終わって再び警察署に帰りつくころにはとっくに夜になっているという事態も普通に起きます。
勾留の要件は以下のように定められています(刑訴法207条1項、60条)。
①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり
②以下のいずれかに当たる場合
ア 被疑者が定まった住居を有しない
イ 被疑者が罪障を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
ウ 被疑者が逃亡しまたは逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
理屈上では、裁判官は検察官から独立した立場で判断を行い、この①②の要件を積極的に満たしていない限り検察官の勾留請求を退けなければならない、となるのですが。
よほど気概のある裁判官に当たらない限り、
「検察官が『勾留の必要がある』と言っているならそうなのだろう」
「悪いことをしたなら普通は証拠隠滅や逃亡を図るものでしょ」
とほぼフリーパス状態で勾留が認められてしまうのが現実です。
裁判官が検察官の勾留請求を却下する割合は5~6%と低い数字に留まっています。
ただこの勾留請求却下率は年代とともに少しずつ上昇はしており、非常に緩やかなスピードではありますが身柄拘束を慎重に判断する裁判官が増えてきていることを示しています。
なお勾留の要件として、実は③勾留の必要性というものも挙げられます。
法令上の根拠は刑訴法87条1項で
「勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは……勾留を取り消さなければならない」
とされていることです。
例えば有罪判決となった場合でも罰金等の軽い刑罰しか用意されていない罪で被疑者を勾留し、そのことによって被疑者が職を失ってしまう可能性があるような場合、勾留を認めることで得られる捜査上の利益と比べて勾留によって被疑者が被る損害が大きすぎるとして勾留の必要性が否定されることがあります。
もっとも「勾留の理由」と呼ばれる上述の①②の要件が肯定されれば、③の「勾留の必要性」も半自動的に肯定され、あとは勾留の効力を争う「準抗告」手続の中で被疑者・被告人の弁護人が勾留の必要性に言及することがある、くらいの位置付けです。
裁判官が勾留を認める決定を下すとそこから原則として10日間身柄拘束されます。
勾留期間中は警察署で警察官の取調べを受けたり、検察庁に連れていかれて検察官の取調べを受けたりします。
勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない事由があると裁判官が認めるときは検察官の請求によりさらに10日間、合計で最長20日間まで延長されることがあります(刑訴法208条2項)。
被疑事実を否認していたり、重大犯罪だったり、共犯が複数いる事件や組織犯罪では勾留が延長される可能性が高くなります。
なお「内乱に関する罪」「外患に関する罪」「国交に関する罪」「騒乱の罪」という国家レベルの特級犯罪に関しては最長25日まで延長が可能です(刑訴法208条の2)。
被疑者を勾留している場合、検察官は勾留満期が到来する前に被疑者の処分を決めます。
一つは被疑者に対する刑事裁判を提起する「起訴」。
もう一つはこの起訴を見送る「不起訴」。
起訴された場合は引き続き勾留(被告人勾留)が検討されます。
不起訴となった場合は釈放されます。
刑事訴訟法
第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
② 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
③ 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。第八十七条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
② 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
② 前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
③ 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
④ 第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
⑤ 裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
② 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
第二百八条の二 裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。