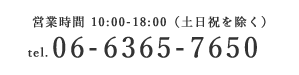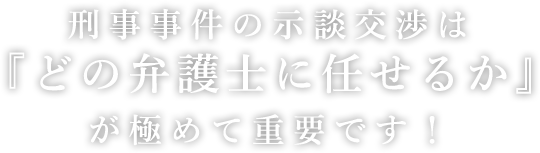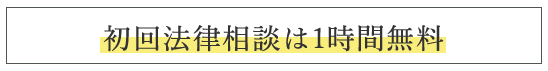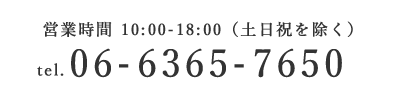示談交渉が失敗するのはどのようなケースですか
-
一番多いのは「被害者が交渉すること自体を拒んだケース」です。次いで「被害者が法外な金額を要求してきたケース」です。
詳細な回答
士道法律事務所は刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士の事務所です。
刑事示談交渉に一点特化して研鑽を重ねていくことで示談の成功率は
被害者との交渉を開始できたケースにおいて約89,4%
という水準に至っています(2024年2月時点のデータ)。
この数字からもわかるように示談の成功率は100%ではありません。
取り扱う事件数が多くなってくると「示談をまとめることができなかった」という事例がどうしても一定数出てきます。
士道法律事務所では過去に受任した刑事示談交渉事件のデータベースを自前で作成しています。
データベースの利用目的としては第一に
新たな示談交渉事件を受任する際に過去の類似例を参照してなるべく正確な予測を立てる
ということが挙げられます。
これ以外にもデータベースの利用価値はあります。
それは示談がまとまらなかったケース、つまり失敗例について、
「なぜ示談をまとめることができなかったのか」
「どうすれば示談がまとまる可能性があったのか」
ということの分析を行い、今後の失敗例を一件でも減らしていくということです。
示談不成立で一番多いパターンは、
「被害者に示談交渉希望の旨を打診したが被害者が交渉自体を拒否した」
というものです。
直近では約16.3%の割合で発生します。
理由のバリエーションはいくつか存在します。
例えば
「警察や検察の方で適正に処分してくれたらいいから」
というもの(関心薄のパターン)。
「公然わいせつ(露出行為を目撃しただけ)」
「建造物侵入(マンションの共用部に立ち入られただけ)」
「器物損壊(支給品の制服を汚されただけ)」
のように被害の程度が小さかったり被害者意識が低かったりするケースで見られます。
例えば
「加害者を許すつもりはないので交渉もしない」
というパターン(怒りのパターン)。
「名誉毀損(SNSに元カノを誹謗中傷する投稿をした)」
「窃盗(元勤務先の物品を持ち帰った)」
「暴行・傷害(元々会社内で不仲だった相手に手を上げた)」
のように従前の関係性から憎悪が増すケースで散見されます。
例えば
「所属組織の規則により示談交渉はしない(できない)」
というパターン(規則のパターン)。
「詐欺(ケータイショップで偽名を使ってスマホを詐取した)」
「窃盗(大手家電店で商品を万引きした)」
「暴行・傷害(酔って駅員に暴力を振るった)」
「詐欺(国から補助金を詐取した)」
「公務執行妨害(警察官を殴った)」
のように被害者本人の属する組織の意向で示談不可が決まっているケースです。
相手方(被害者)の連絡先がわかっている場合には、これらのケースでも電話をかけたり手紙を送ったりすること自体はできます。
しかし、基本的にこれらの相手方(被害者)は気まぐれで交渉を拒んでいるのではありません。
ちゃんとした理由があって交渉を拒絶しているのです。
そういう相手に電話をかけても取り次いでもらえませんし、手紙の返事は返ってきません。
過去には依頼者の強い要望を受けてこういった対応を試みたこともありますが、効果がないことは実証済みです。
加害者側の自己満足にしかならず、場合によっては被害者の感情を逆撫でにして状況が悪化する恐れもあります。
そのため、こういったケースに該当する場合はそれ以上不用意な働きかけをしないのが鉄則です。
ただし、例外があります。
それは
・警察官の対応が信用できないケース
・時間の経過で被害者の態度軟化が予想されるケース
です。
まず前者について、ハッキリ言ってしまうと
警察署や警察官によって「アタリ」「ハズレ」が存在します。
弁護士から警察署に
「示談交渉をしたいので被害者の意向を確認してOKなら連絡先を教えてほしい」
と伝えると、大体の警察官は被害者と連絡を取ってくれます。
「アタリ」の警察官だった場合は迅速に被害者に連絡をつけてくれたり、場合によっては被害者を説得してくれたりすることもあります。
逆に「ハズレ」の警察官に当たってしまった場合。
理由をつけて被害者への連絡を拒んだり、場合によっては被害者に誤ったことを伝えて示談を妨害してきたりします。
にわかには信じ難い話でしょうし、示談の妨害まで行くのは極めて稀なケースではあるのですが、確かに存在します。
なぜそんなことがわかるのかと言うと、後日検察官を通じて連絡を取ることのできた被害者から
「警察官から『加害者の弁護士と交渉などしなくていい』と言われたんですけど」
「何でこんなに連絡が遅かったんですか(=警察官が示談の話を伝えていない)」
と言われたことが何度かあるからです。
また、被害に遭った直後は被害者も頭に血が上っていることが少なくありません。
しかし時間が経って少し冷静になったり、周囲のアドバイスを受けたりして
「とりあえず話だけでも聞いてみようか」
と態度を変えることがあります。
こういうことがあるので、明らかに無理なケース以外では、警察段階で一度示談交渉を断られても送検後に検察官を通じて再度示談の意向確認をしてもらうことがあります。
これによって一度途絶えたはずの示談の道が復活することもあります。
このように再打診を試みることはありますが、結局示談交渉を開始することすらできず、「示談不成立」で終わるケースも一定割合存在します。
もっとも、示談が不成立となっても
・刑事贖罪寄付を行う
・被害者側に一方的にお金を振り込む
・「なぜ示談が成立しなかったか」を検察官に報告する
という次善の策を講じることで不起訴になったり略式手続(略式起訴)で済んだりすることはあるのですが。
とはいえこれが最も多い「示談交渉失敗」のパターンとなります。
示談失敗のパターンとして次に多いのは
「被害者が法外な金額を要求してきた」
「加害者が弁護士のアドバイスを無視した」
というものが挙げられます。
一つ目の「被害者が法外な金額を要求してきたケース」について。
示談交渉で一番の争点となるのは「解決金(慰謝料・示談金)の額」です。
士道法律事務所は刑事示談交渉に特化しているので、自前でデータベースが作れるくらいには解決事例を積み上げています。
そのため、法律相談で事実関係を聴き取り、被害の程度、犯行に至る経緯、加害者と被害者の関係性、被害者側弁護士の有無等を確認すればこのデータベースと照合させて
「この事件は大体このくらいの範囲で示談がまとまるだろう」
ということを予想することができます。
この予想が大きく外れることはそうそうありません。
しかし、ときどき無茶苦茶な金額を要求してくる被害者に当たることがあります。
具体例を挙げると以下のようなものです。
・風呂場の盗撮(解決金の目安は25~50万円)で500万円要求
・不同意わいせつ(解決金の目安は50~100万円)で300万円要求
・暴行(解決金の目安は20~40万円)で「数千万円の腕時計に傷がついた」と言いがかりをつけて200万円要求
こういったケースでは真面目に交渉しても無駄です。
なので示談交渉はさっさと打ち切り、検察官宛の意見書で
「こちらは適正額を提示しましたが被害者が無茶な金額を要求してきました」
と交渉経過を報告し、それで不起訴処分や略式起訴を取るようにしています。
二つ目の「加害者が弁護士のアドバイスを無視したケース」について。
これは加害者と被害者が事件前から知り合い同士だった場合や、罪名が「暴行・傷害」や「器物損壊」の事案で稀に発生します。
これらのケースでは依頼者(加害者)が、
「被害者は○○という性格だから××というやり方で交渉を進めてくれ」
「先に被害者が××してきたせいで手を出したのでその点を追及してほしい」
といった要望を弁護士に伝えてくることがあります。
依頼者(加害者)としては
「被害者のことは弁護士より自分の方が理解している」
「被害者にも非があったことをわからせてやりたい」
といった思いでこういう要求を出すのでしょう。
残念ながらそのやり方で事態が好転することはありません。
加害者・被害者の関係になった時点で過去の人間関係は破壊されています。
被害者側の非をあげつらったところで被害者が矛を収めることなどあり得ません。
水掛け論の末に被害者感情最悪化というどうしようもない結果が残るだけです。
士道法律事務所は
適正な進め方、適正な金額で、十分な確実性をもって示談をまとめること
に重きを置いています。
相場より低い金額で被害者を納得させたい。
被害者にも非があることをわからせてやりたい。
そういう気持ちを抱くこと自体は否定しませんが、そこに重きを置くのであれば
必然的に「示談成立の確実性」への優先度は下げざるを得ません。
なぜこの金額での示談を勧めるのか。
なぜこういうやり方で示談交渉を行うのか。
弁護士が理由も含めてきちんと説明すればほとんどの依頼者は納得してくれます。
しかし、どうしても考えを曲げてくれない場合は依頼者の指示通りに行動するしかありません。
その結果、「示談失敗」の確率は跳ね上がることになります。
弁護士は単なる伝言係、メッセンジャーではありません。
特に刑事示談交渉に豊富な経験を持つ弁護士はその道のプロフェッショナル、エキスパートです。
自分が依頼した弁護士をちゃんと信頼してアドバイスを受け入れることが示談成功の可能性を高めることに繋がります。
最後に、極めて稀なケースですが、
「被害者の性格や考え方が特殊過ぎて示談交渉が頓挫した」
という例も存在します。
【ケース1】
警察から「被害者が話を聞いてもいいと言っている」と言われて被害者に電話したところ、「弁護士が話をしたいというから連絡先を伝えただけで、示談する気は全くない」と言われ、本当に謝罪の言葉を伝えるだけで終わった。
【ケース2】
被害者に電話をかけるも、話し始めて1分もしないうちに「疲れた、気分がすぐれない」と電話を切られた。日をおいて何度か電話をかけ直すも応答がなく、示談の本題(示談の意味やこちらが考えている解決金の額等)を伝える前の段階で連絡が取れなくなってしまった。
【ケース3】
被害者の被害感情が強く、示談にあまり乗り気でない様子が伝わってきた。そこで確実に示談をまとめるために依頼者と相談して相場より高めの金額を提示したところ、「え、怖い、引く」と言われて示談を断られた。
いずれも示談不成立の理由としてある意味理不尽で特殊過ぎるレアケースであり、たまたま巡り合わせが悪くて不幸な事故に遭ったようなものではあるのですが。
被害者の心情等に対する読みの精度をもっと上げていけばこういった特殊事例でも上手に示談をまとめられる可能性を高められるのではないか。
士道法律事務所はそのように考え、日夜研究と修正を積み重ねています。